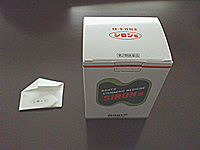日々の出来事や写真、過去の小文、その他諸々を取り上げます。
表題はホームページのタイトル候補だったのですが、咽(喉の上の方)、喉(喉の下、首のあたり)ということで落選しました。しかし因業に音が同じなので、わがままでかたくなな性格の自身にふさわしいと思い表題に復活させました。
方言に囲まれた暮らし
昭和60年、神戸から勤め先に近い滋賀県守山市に転居してから同県には30年、愛媛県今治市には7年間居住し、その間鹿児島市、新津市、廿日市市、清洲町などに長期出張したことも・・・。
その転居地や出張先で、地元関係者と初めて会った時「あなたは関西弁風の言葉をしゃべるが、自分の知っている関西弁と何かが違う、生まれはどこだ」という意味のことをよく聞かれました。
関西以外に居住している人はテレビに登場する大阪出身のタレントやお笑い芸人の影響からか「関西弁」=「大阪弁」と認識している人が多く、小生が異郷で話す「滋賀県南部方言の影響を少し受けた神戸弁に(聞き手が理解しやすいように)標準語を交えた言葉」は違和感を与えるようです。
そんなわけで初対面時には自分の「出身地と言葉」についてしかたなく話すのですが、結構面倒なことでした。
さらに異郷で仕事する折は、
「その地の方言を聞いて」→「自身の方言に翻訳し」→「滋賀県南部の方言の影響を少し受けた神戸弁に標準語を交えた言葉で答える」
という複雑な「言葉の認識・表現」をしなくてはなりません。
それでも数か月たち当該地の方言に慣れ「一定のパターン」をおぼえたころには、仕事が終わり帰還。別の出張先に出るとまた一からやり直しです。
2年前、定年退職を機に30年ぶりに帰郷し地元の福祉施設にパートに出ると、当然多くの職員が神戸弁をしゃべっているので、コミュニケーションにおける上記の「複雑な手順」は必要なくなりました。
「短い文章」や時には「単語」を話すだけで「意向」どころか「裏の意味」まで通じてしまい、慌てることがあります。
神戸で就職し、同じ方言に囲まれた生活を定年まで続けていたら「コミュニケーションに係るストレス」もなく頭痛や肩こりが随分減ったでしょう。
いまさらどうしようもないことですが。
鯵も大きくなりました
塩屋のベラ釣
納曽利
昨年10月、東灘区の「うはらホール」で「熱田神宮 巡回講演」が実施されることが新聞に掲載されたので、早速応募すると入場券が当たりました。
当日、開演時間(18:30)の少し前に会場に着くと、500席以上ある会場は、ほぼ満員の盛況で、名古屋弁の案内係が、入場者をさばくのに大わらわの様子。
定刻になると司会者が登場し、講演責任者の挨拶の後、いよいよ始まりです。
最初のプログラムは雅楽「越天楽」ですが、司会者によると、
「熱田神宮では、巫女も雅楽や舞楽の練習を行い、今回も楽人として演奏する」
ということで、女性楽人も交えた少人数の楽人により演奏されました。
次は「巫女さん」数名が本来の装束で登場し、楽に合わせて「三種の神器 草薙剣」をテーマにした神楽「みつるぎ」が優雅に舞われます。
三番目は公演のメイン「杉山 直氏によるヤマトタケルノミコトの神話朗読」。
スクリーンに映されるさまざまな映像と共に感情豊かに語られる「日本武尊の一代記」を聞き、忘れかけていた古事記の関係記述を思い出しました。
公演の最後を飾る舞楽「納曽利」の上演前、司会者から、
「本日は巫女が稚児舞によって行うので、面は付けず、花飾りを付けた天冠をかぶります」
という説明があったので「簡略パターンか」とやや失望しましたが、小柄でかわいらしい二人の女性が演じる舞は「軽やか」そのもので実に魅力的です。
小生は (小野摂龍楽頭が鞨鼓を掻いていたので、昭和の終わりか平成の初め頃)「雅亮会」の公演でこの舞を鑑賞したことがありますが、その時は、男の舞人が牙の付いた恐ろしげな面を付け、重々しく勇壮に舞っていました。
しかし「納曽利」は「瑞兆とされる龍が、天空で楽しげに舞う様子」をあらわす舞ですから、当然浮遊感があっていいはずで、今回の女性の舞人が演じる「ふわふわと飛んでいるような舞」もまたその本質を示しているのではないでしょうか。
舞楽の奥深さを堪能する素晴らしい時を過ごすことが出来、満足して帰宅しました。
「世間をお騒がせしてすみません」
横溝正史作「人形佐七捕物帳」の一場面。
春のうららかな午後、しばらく事件のない平和な江戸「佐七」は恋女房に膝枕で耳掃除をしてもらい、子分の「きんちゃくの辰」は鼻毛を抜き「うらなりの豆六」は草双紙を読みながら居眠り。
将軍様のありがたい御政道は江戸の隅々までいきわたり、天下泰平、鼓腹撃壌「岡引き」や「瓦版屋」はすっかり無聊をかこつ有様。
しかし、そんな平安もやがて「とんでもない事件」に打ち破られ、親分子分うち揃ってあたふたと家を飛び出してゆくのですが。
平穏な日常だと「警察」や「マスコミ」が暇なのは、現在でも全く同じです。
昭和の頃知り合いだった「社会部記者」も事件のない日は、「支局」や「警察記者クラブ」の片隅に過度の酒とたばこのせいですっかり張りのなくなった顔で所在なげにくすぶっているのですが、事件の一報が入った途端、たちまち元気を取り戻し、カメラマンや後輩記者を引き連れてばたばたと出動するのが通例でした。
ところで「世間をお騒がせしてすみません」というお詫びの文言は「事件」や「事故」に関連して行われる「記者会見」で当事者がよく用います。
小生はこれを聞くたびにいったい誰を対象にしたお詫びなのかずっと疑問を持っていました。
まず、お詫びの対象である「世間」とはそもそも何でしょうか?
三省堂『新明解国語辞典』第七版-2016年-によると、
「一般の人々が集まって形作る社会。また、それを形作る人びと」
と、書かれています。
「社会」や「人々」の範囲が特に限定されてないことから「世間」とは「日本社会」いや、もしかすると「地球上の社会」のことかもしれません。
しかし、タレントの「不倫」や「二股疑惑」が「全世界」に悪影響を及ぼすとは思えませんし、どうしても「不行跡」を詫びたいなら、実際に損失を被る「所属プロダクション」「スポンサー」「テレビ局「「興行関係先」「ファンクラブ」等に個別に誤りに行けばいいわけで、事件に関係のない視聴者に謝罪する必要性はあるのでしょうか?
そもそも、タレントがテレビでお詫びしても、視聴者の多くは損失を被ったわけではないので対応のしようがありません。
また、この文言は当事者が「将軍様(総理大臣閣下)の立派な御政道により岡引き(警察)や瓦版屋(マスコミ)が無聊をかこつような平和すぎる世の中の秩序を乱す事件を起こしたことを詫びる」ために用いており、事件そのものの違法性を詫びてはいないのです。
聞くたびに不信感を抱いている小生のような「世間の一員」もいることですし、当事者もこの「手垢のついた」「無責任な」言葉を使うことはもういいかげんやめるべきでなないでしょうか。
さて、蛇足ですが記者会見での「マスコミの皆様」は「国民の代表として質問している」とよく言われますが、当事者と利害関係のないことが多い小生が「国民の代表」に選んだ覚えはありません。
この「国民の代表」は記者会見で当事者に対して「適切な答がない」などと声を荒げたりしていますが、実際は大きな事件や天災がないと「天下泰平時の佐七」のように暇で困ってしまう立場なので、「世間を騒がしてくれてありがとう」という本当の思いを心に秘めて「記者会見」臨んでいることは間違いないと思います。
三毛媛と仲間たち(インドネシアの猫さん、猫君)
ブログを始めた頃「三毛媛」のことを紹介しましたが、最近パソコンのハードディスクの片隅にインドネシアで撮影した猫の写真データが保存されていたのを見つけました。
当地の猫の体の文様は、日本猫と変わりませんが、顔はシャムネコのように「長いもの」と「やや長めもの」が大半で、日本猫に見られる「鞠」か「豚饅」ような「ぽっちゃり顔の猫」は見た記憶がありません。
「やや長めの顔」で「顎が細く」「目も大きい」美形猫が多いようです。
彼の国はイスラム教国で、猫は大事にされ可愛がられているせいか、初対面の人にもすぐなついてくるので、猫好きの方は一度訪ねられてはいかがでしょうか。
受診の思い出(3)
3、静脈注射
小学校3年生の時、祖父が亡くなりました。
肺に疾患を抱えていましたが、夕食は普通に食べ、就寝したのに、翌朝急死したのには、家族全員びっくり仰天です。
父もよほど動揺したのか、小生のような「小学生ごとき」に向かって深刻な顔で「人生いろいろなことがある」などと述懐していましたが、気を取り直して向かったのは、実家から歩いて4~5分のところにある内科医院だったので、前出の老先生はもう亡くなったか、医院をたたんでいたのでしょう。
小生もこのころから、そこで診察してもらうようになりました。
医院は「職住同一」の老先生の所と違い、店が何軒かある表通りに面した「専用の建物」で、ドアを開けるとすぐ待合室があり、奥に受付のガラス窓があるのですが、薬の調合は受付のずっと奥の方で行っているらしく、窓から見えないので、受診時の二つの楽しみ(調合の見学、市電の乗車)は残念ながら消滅することに。
ところで、ここの先生は喘息治療に静脈注射を用いていました。
その手順は「長さが10㎝位の太いアンプル」と「小さなアンプル」合計2本の口を切り、長さが17センチ位、直径も2㎝以上ありそうな大きな注射器にまず「太いアンプル」、次に「小さなアンプル」から注射液を吸い込むと、看護婦さんが消毒したひじの内側に針を刺すのですが、先生の腕がいいのかあまり痛くありません。
針を刺してから何度か押引きして、注射器が安定するとゆっくりピストンを押してゆきます。
痛くないといってもやはり注射は怖いので目を反らしたいのですが「徐々に注射液が腕に入ってゆく様子」には大変興味があり、目を反らしたり見つめたりしているうちに、半分位注入が済むと、先生は必ずピストンを停め、少し引きます。
すると注射器内に血液が糸をひくようにスーと入って来て、ゆらゆらゆれて広がり、透明な注射液は濁ってしまうのです。
きれいな注射液が血で汚されるのは嫌なので一度顔をしかめたことがあります。すると先生は気分が悪くなった勘違いし「大丈夫?」と言って針を抜いてしまいました。
その時は「しまったせっかくあの液が全部腕に入るのにもったいないことをした」と後悔し、それ以後注射中は務めて無表情を装うことにしましたが、はたから見るとその不自然さは随分滑稽に見えたでしょう。
この注射の効き目は早く、注射液が全部腕に入る前に喘息の発作が「すー」と嘘のように遠のいてゆくので気に入っていました。
しかし、近年は点滴に取って代わられたらしくとんと見かけません。
幼い時の記憶に「受診体験」が多く含まれているのは、小児喘息のため度々受診し、怖い場所ではあるのですが、反面好奇心をくすぐる事象がそこここにある医院という異次元の世界での様々な体験が記憶として長く残されたからでしょう。(この項終わり)
受診の思い出(2)
2、チミツシン
かかりつけの内科で渡される「粉薬」は子供でも飲みやすいように、少し甘みがついていましたが、美味とは程遠いものだったので、オプラートに包んで飲んでいました。
逆に飲むのが楽しみでだったのが、一緒にもらう「喘息の飲み薬(チミツシン)」です。
その臭いは強く、味もおいしいものではないのですが、甘味は結構あり、飲み慣れてしまうと何故かおいしく感じるようになる不思議な薬でした。
冷蔵庫で十分冷やした薬瓶を食後に出し「瓶の側面に刻まれた1メモリ分の薬液」を慎重に計って湯飲みに入れ、ジュース感覚でゆっくり味わって飲むのです。
ところで、当時祝い事や忘年会等で家族、親せき一同集まって出かける三宮の中華料理店があり、そこではいつもコース料理を頼むのですが、最後のデザートに出て来るのが大きなボウル一杯の「杏仁豆腐」で当時は「中華プリン」と呼ばれていました。
もちろんケーキ屋さんで売られている一般的な「西洋プリン?」と違い「カルメラ」もかかっていません。
「杏仁」の割合が多いのか、現在市販されているマイルドな杏仁豆腐と比べると「臭いも味も」強烈でした。そして何故かその両方が「チミツシン」のそれとよく似ているのです。
「チミツシン」の主成分は「咳止め」「痰切り」の効果がある「杏仁(あんずの種)」であることを知ったのは、ずっと後のことだったので、当時は「咳止めの薬」と「中華料理のデザート」が同じ味なのはずいぶん不思議なことだと思っていました。
近年、薬膳料理など漢方薬を用いた料理がもてはやされていますが、50年前から(おそらくもっともっと以前から)漢方薬は中華料理の材料として当然の如く用いられていたのでしょう。
幼いころの「陰の思い出(受診)」と「陽の思い出(中華料理の会食)」に「杏仁」という共通項があったというお話でございました。(続く)
受診の思い出(1)
1、上皿天秤と薬包紙
幼稚園から中学生までの間(昭和30年代から40年代初め頃)小生は持病の小児喘息発作が月に何度も起こり、その度「掛かりつけの内科医院」に連れて行かれました。
そこは「最寄り市電停留所」の「次の停留所」近くにあるので、たいてい父と市電に乗って出かけます。
発作で苦しいのに市電に乗った途端、ずっと乗っていたくなるのですが、残念ながらすぐに下車し、大きらいな細い坂道を下って「医院」まで歩かなければなりません。
この道の街灯は電球のため街は暗く、その上途中に「マムシ酒」の大きな瓶をウインドウに飾っている店があり、それが怖いので店の前を通る時は反対側に目を反らします。
この難所?を過ぎると未舗装の広い道が坂道に交差していて、東に曲がるとようやく目的地が見えてきました。
「医院」は大きな看板は出ているのですが、外観は普通の和風家屋で、玄関を入り右の廊下に進むと受付のガラス窓があり、窓の向こうに座っている看護婦さんに保険証を渡し、庭に面した廊下をさらに進み、右側の扉を開けると中は帽子掛けとソファとある待合室になっています。
ソファに座ってしばらくすると、看護婦さんに呼ばれ、父と一緒に診察室に入ると蓋の端から湯気をさかんに噴き出している「注射器の煮沸消毒器」が脇の棚の上にあり、大きな机の左側に老先生が座っていました。
入室し、机の前の丸椅子にちょこんとのると、先生は小生とそばに立っている父から病状を聞き、聴診器で胸にあて「何時もの発作ですなあ」と毎度おなじみの診断結果を宣い、横の棚から「薬液のアンプル」を出し「ハート形のヤスリのような小カッター」で首のところを少し削り、アンプルの先をもって折ると「ポン」と音がして先の部分が取れます。
すかさず看護婦さんが「煮沸消毒器」の脇にあるケースから細い注射器を出して先生に渡たすと、消毒液の付いた脱脂綿で小生の「二の腕」を消毒。
先生は注射器でアンプルから注射液を吸い取って、上を向けてピストンを動かし針から空気を押出すと、針が腕にズブリと突き刺ささり、とても痛いはずなのですが、痛みの記憶は全くないのです。
実は、この先生「皮下注射を痛みなく打つ不思議なテクニックを持つ魔術師だった」のかもしれません?
無事診察が終わると、薬の調合が終わるまで待合室で待つのですが、小生は父を部屋に残し、受付へ行き、窓から看護婦さん(薬剤師さんだったのかもしれません)が「薬を調合」する様子をじっと眺めるのが定番となっていました。
その「調合」を最初から順を追って記すと、まず先生の持ってきたカルテをも見て、横の棚から「茶色の瓶」を幾つか、机の抽斗から「硫酸紙」を何枚か取出します。
次に「上皿天秤」の片方に分銅を南個か載せ、反対側の皿には「硫酸紙」を置き、銀色の匙で「瓶」から「薬の粉末」を掬い、その上に載せて、釣合の取れるまで粉薬の増減を実施。
「出した瓶」全てから粉薬を掬い出し、定量にすると、それらを一つの「乳鉢」に入れ「乳棒」で混ぜ、新たに取出した「大きな硫酸紙」にあけますが、その時乳鉢や乳棒に付着した粉末は「小さな刷毛」で丁寧に「紙」に落とされます。
最後に皿の片方には、先ほどよりずっと小さな分銅が、もう一方には「薬包紙」が置かれ「大きな硫酸紙」上の粉薬を「先ほどより小さな匙」を使って少しずつ「薬包紙」に移し、釣合が取れると「紙」は降ろされ、手早く折りたたまれました。
薬が配分された十数枚の「薬包紙」全てをたたみ終えると、飲み薬に取り掛かりますが、こちらは大きな瓶から「茶色の飲薬」を目盛りの付いた小瓶に移すだけなのですぐ終わります。
薬の調合が終わり、待合室に連絡がゆくと、父が出てきて会計を済ませ、薬をもらい、元来た坂道を戻るのですが、発作で息苦しい上「マムシ」が怖い往路と違い、症状も少し軽くなり、甘い飲薬までもらっているので気分は軽く「市電の停留所までの坂道を元気よく登っていこう」意気込むのですが「マムシ」の前まで来るとやはり怖さに耐えられず、往路同様目を反らし通り過ぎるのでした。(続く)
※「看護婦」という言葉を用いることは現代にあっては不適切かと思われますが、拙文は半世紀前の記憶の再構成であり、この言葉も当時は一般的に用いられていながら、現在は歴史的用語としてしか存在しえないことを認識した上で用いています。
これが薬包紙です
シロンSは今でも薬包紙を使っています
平成30年 初釣行
5月中旬某日今年最初の釣行を実施しました。
しかし毎年初釣行の釣場に決めている「須磨海釣り公園」が、当日定休日のため、やむなく行先を塩屋防波堤に変更。
最寄駅からJRに乗車し「海釣り公園」なら園内で餌を買うところを須磨駅で途中下車し、餌店で石ゴカイを購入して駅に戻ったところ、駅東方の「上りの急行線」には新快速「緩行線」には快速が停まっていて「須磨駅と須磨海浜公園駅間の踏切で緊急停止ボタンが押されたため、すべての列車が停まっています」との構内放送が繰り返し流されています。
「あちゃー、もしかして今日は三隣亡?」と落胆し「JRをあきらめて、山陽電車で塩屋に行こうか?」と思いつつも「しばらく待つか」と、ベンチに座ってミネラルウオーターを飲んでいると、突如「緩行線」の快速が動き出し、徐行運転で東方へ消えてゆきました。
5分後、新快速も出発し、ほどなくして「全線開通」のアナウンスがあり、7~8分後須磨駅に到着した乗客満載の各停に乗車、予定より30分以上遅れて、ようやく塩屋防波堤に着きました。
まず、防波堤の先端まで行き「ノベ竿」を出しましたが、何度振り込んでも魚信はなく、餌にはかじられた痕もありません。
まだ水温が低いので「魚は深場にいるかもしれない」と、「投竿」で沖目を狙ってみたのですが、根がかりするばかりで全く魚信なし。
そのうち「ノベ竿先に結んだ糸がほどけて仕掛けをすべて流してしまう」という大惨事が起こり「9年間続いた坊主なしの記録が今日遂に途絶えてしまうのでは」という不吉な情景が脳裏に浮かんできました。
仕方なく昨年、テンコチやキスが数多く釣れた防波堤の根元に行って砂地に座っている石の周りを探ると「小さな小さな魚信」が何度もあり、合わせるのですが、釣針に乗りません。
それでもしつこく探っているとついに5cmほどの「ミニテンコチ」が釣れたので、直ちに放流して、納竿。正常に動き始めたJRで早々と帰宅しました。
今回は「坊主なし記録」が途切れることはありませんでしたが、実は近頃、記録を続けていくことに精神的な負担を感じていて、鳥谷の連続試合出場記録も5月29日に途切れたことだし、そろそろ「記録を途絶させ、気楽な立場になりたい」という思いが心の中に芽生えつつあります。